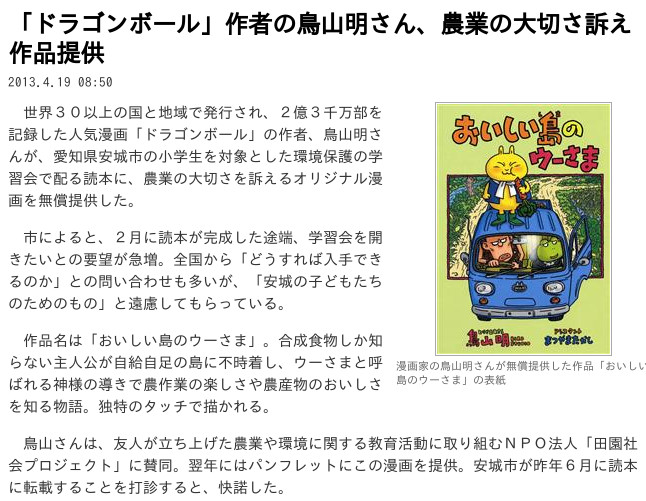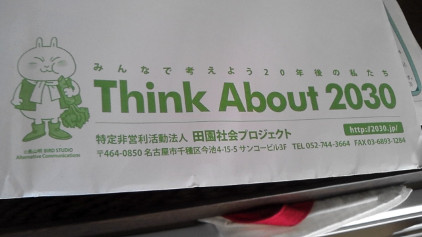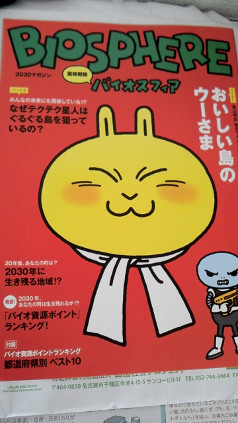ちょっと前に本屋で見かけて面白そうな内容なのと、著者が「独立行政法人酒類総合研究所」という、「え?公的機関にそんな名前のトコロあんの!?」という釣り針にみごとに引っかかり購入した一冊。

独立行政法人酒類総合研究所は本当に実在し、酒税の適用などを行なっているそうです。つまり、ビール党である我々としては憎き相手。メーカーによる発泡酒・第三のビールの努力を「無駄無駄無駄無駄ぁ」って叫びながら「税金よこせゴルァ」と言っている部門ということだ。オイオイ、けしからん部門じゃねーかw。
そんな機関が、お酒の知識を清酒・焼酎・ワイン・ビール・スピリッツとブランデー・リキュール・その他醸造酒・合成清酒・みりん・粉末酒・雑酒にわけて浅く広く歴史と作り方を教えてくれる。
いや、正直楽しんで読めましたよ。めったに飲まないブランデーはウィスキーと同じ穀物から作る蒸留酒かと思ったらあれ葡萄から、ワインを蒸留して作るお酒だったんですね!全然知りませんでしたわー。焼酎の甲乙も作り方で蒸留方法が違うぐらいしか知りませんでしたが連続式・単式の違いがはっきりわかったのはこの本のおかげです。ええ、不勉強なだけですよ。だってただの酔っぱらいだもの♪。
あとは、「山廃仕込み」が「山卸(やまおろし)」という蒸米とこうじを混ぜたものを櫂(かい)ですりつぶす作業があるんだけど、これを速醸酛(そくじょうもと)と呼ばれる強い乳酸菌を使うことで止めたから「山廃」というってのが一番「ぺー」って思ったかな。
あんまり酒の事良く知らない人は為になる一冊だと思います。日頃飲む専門の人もちょっとかじってみるといいかもよ。
最後に、愕然とした一文を引用して今日の日記を終えましょう。
焼酎の酔い覚めのよさを指摘する人がいます。その真偽のほどは明らかではありませんが、一般にお酒は料理をきちんと食べながら適用を飲むと、酔いが軽減される傾向にあります。正しい飲み方があっての酔い覚めの良さなのかもしれません。
ガ━━━(゚Д゚;)━( ゚Д)━( ゚)━( )━(゚; )━(Д゚; )━(゚Д゚;)━━━ン!!!!!
うん、やっぱりそうだよね…。
 2013年の夏休みに上野美術館で見たラファエロ展で買った「キリスト教絵画の見かた」ですが、とってもおもしろかったのですよ。ほら、りょうすけは宗教に詳しくないのでキリスト教も全く知らないので参考になった。
2013年の夏休みに上野美術館で見たラファエロ展で買った「キリスト教絵画の見かた」ですが、とってもおもしろかったのですよ。ほら、りょうすけは宗教に詳しくないのでキリスト教も全く知らないので参考になった。