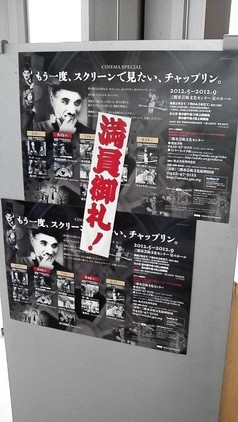 チャップリンって知ってはいたけど観たことなかったんですわ。それが三鷹市のイベントで月1回のペースで9月までチャップリン作品を上映するイベントをやると聞いて参加してきましたよ。今日のチケットは売り切れ。結構注目されてるんですね。会場に入ると客層は思ったとおり結構高齢。学生風の人もチラホラ、子連れの親子もチラホラしてますが、基本はセカンドライフっぽい人ばかり。
チャップリンって知ってはいたけど観たことなかったんですわ。それが三鷹市のイベントで月1回のペースで9月までチャップリン作品を上映するイベントをやると聞いて参加してきましたよ。今日のチケットは売り切れ。結構注目されてるんですね。会場に入ると客層は思ったとおり結構高齢。学生風の人もチラホラ、子連れの親子もチラホラしてますが、基本はセカンドライフっぽい人ばかり。
さて、今日の上映作品は「キッド」(1921年)と「街の灯」(1931年)です。
「キッド」は 、捨て子を拾ってしまったチャップリンが本当の親子のように二人で生活する。最後は子の本当の母親が見つかる、という話。「街の灯」は盲目の花屋少女は花を買ったチャップリンを金持ちと勘違いするが、彼女に恋したチャップリンはけなげに助けようと努力し、最終的に目が見えるようになった少女が、手をさわっただけで金持ちではないチャップリンを「彼」だと気付く話。
どちらも貧しく、生きるのが不器用な主人公。子供のために、彼女のために奮闘しなかなか報われないのだけど、最終的には…ってでもあれハッピーエンドなのか?ハッピーエンドになるんだよね?と想像させられるエンディングではあった。
1921年といえば、第一次世界大戦が終わり、上向き景気だったころのハズ。このなかでホームレスのような主人公というのはよく見る風景だったのだろうか。「キッド」的には戦争孤児の扱いを考えさせる作品になったのかもしれない。
「街の灯」の1931年は「暗黒の木曜日」の2年後で不況の待っただな中のハズ。このチャップリン風のホームレスも多くいたのだろう。作中に子供が新聞を売る風景もあったのでホームレスは珍しくない風景だったかもしれない。酔って主人公を慕う金持ちはどういうポジションだったのだろうか。破産うんぬん言っていたので金融業だったかもしれない。
チャップリンのこの2作は、「トムとジェリー」や「ドリフターズ」への影響がよくわかる。「キッド」で子供が喧嘩するシーンを煽るチャップリンは「トムとジェリー」でよく見る風景、チャップリンの仕草は志村けんが受け継いでいるように見える。
いやぁ、本当に面白かった。あと5日分あるけど、時代背景とかなるべく勉強してから全部参加する方向で積極的にがんばるわ。